狂気的な男の愛は
女を終焉へ向わせるので
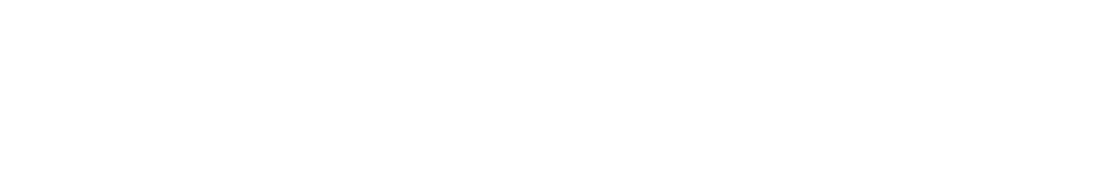
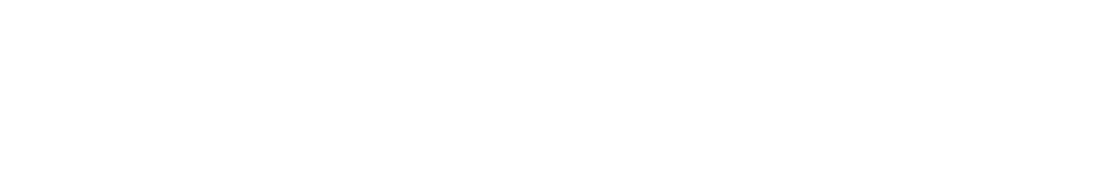
その日、イルミは大して飲みたくもない酒を飲みながらカウンターに並べられた三枚の写真に目を落としていた。どれも場所は異なるものの中心に写るのは同じ女で、一枚目はカフェのテラス席でコーヒーを飲んでいる写真、二枚目は大きな紙袋を持って街を歩いている写真、三枚目は背中の下着のホックに手を伸ばしている姿の写真である。
「でね、は恥ずかしがり屋でちょっと怒りっぽいところがあるけど、そこがすごく可愛いんだ。ハンターとしての資質はイマイチだけど、殺し屋としては……そうだなあ、イルミほどじゃないけど及第点ってところかな。ほんの少し虐めただけで顔を赤くして潤んだ瞳でボクのことを睨んでくるもんだから、もう理性を保つのも大変でさ」
イルミが傍らに置いていたグラスを手に取ると、カランと音を立てて中の氷が揺れた。
「オレ、ヒソカの妄想に付き合ってる暇ないんだけど」
「失礼だな。はちゃんと実在するボクの恋人だよ」
ヒソカはそう言って、不満そうに目を細め唇を尖らせた。イルミは返事をせずに、グラスの中の酒を喉に流し込む。そしてとん、と一回、写真を爪で叩いた。
「じゃあどうして写真が全部盗撮なの」
「言っただろう、は恥ずかしがり屋なんだ」
うっとりと宙を見つめながら話すヒソカから視線を逸らし、イルミは長いため息を零した。
仕事を一つ頼みたい。数日前にそうヒソカから連絡を受けたとき、ちょうどイルミは大きな仕事を終えてククルーマウンテンの自宅へ帰宅したばかりだった。ヒソカのことだからろくな仕事でないことは分かっていたが、報酬は言い値でいいと言われ、そういうことならとイルミは二つ返事で引き受けたのだ。
しかし、である。まさかヒソカから指定されたバーで恋人との馴れ初めや惚気話を聞かされると思っていなかったイルミは、一杯目を飲み終える前からここに来たことを後悔し始めていた。これといった結末のない話をだらだら聞き続けることと人を殺めることならば、圧倒的に後者の方が楽である。
「で、そろそろ本題に入ってくれない? オレはこのヒソカの恋人を殺せばいいわけ?」
耐えかねたイルミが話を先に進めようとそう尋ねれば、ヒソカは重ねた写真に向かって「まさか、殺さないよ」と囁いた。帰ろうと立ち上がったイルミをヒソカは緩やかに制する。
ヒソカの話はこうだ。彼の恋人であるはいつも仕事を終えたあと、近くのバーで軽く飲んでから帰宅する。あと一時間もすればここへ現れるであろう彼女を口説いてほしい。それがヒソカからの依頼だった。
黙って話を聞いていたイルミだったが、さすがに驚いて目を見張った。
「え、口説くの? オレが?」
「イルミに口説かれて困っているところにボクが颯爽と現れるわけさ。しばらく会っていなかった恋人が助けに来る……最高にロマンチックな再会じゃないか」
「仮に、オレに口説かれて満更でもなさそうだったらどうするの」
「そんなはずはないよ。彼女はガードが堅いから」
謎の自信に満ち溢れているヒソカに向かって、イルミはふうん、と呟いた。
そもそもそんな回りくどいやり方をせずとも、恋人なら普通に声をかければいいじゃないか。そう思ったイルミだったが、写真を見つめたまま鼻歌を歌うヒソカを眺めながら何も言わずに残っていた酒を飲み干す。
「あと、これをうまく彼女のグラスに入れてくれるかい」
写真の次にヒソカが置いたのは、透明な液体の入った小瓶。何が入っているのかイルミが尋ねれば、ヒソカは遅効性の媚薬だと言う。
にこにこと楽しそうに微笑むヒソカと暫し見つめ合ったイルミは、ずっと頭の中で考えていたことをとうとう口にした。
「彼女、本当はヒソカの恋人なんかじゃないんだろ?」
「恋人だよ。なぜならボクがそう決めたからね」
やはり自信満々にそう答えたヒソカの目の前で空気がぴり、と震える。空気を切って迷いなく飛んでいったのは、数本の針。おや、と思ってヒソカが目線だけを横へ動かせば、それらはカウンターの奥にいたこの店のマスターの両目と額に命中していた。
おかしな呻き声を漏らしたマスターが、いくつかのグラスを道連れにしてどさりと床へ倒れ込む。客はヒソカとイルミの二人だけ。店内が静まり返る。
ヒソカは驚くことなく、頬杖をついて針の持ち主であるイルミへと視線を向けた。
「なんで殺しちゃうのさ」
「口説くとか面倒だからさー。だったらソイツに化けて薬飲ませる方が簡単だし」
で、薬が効いてきた頃にヒソカが現れて介抱してやればいいだろ。それも十分ロマンチックだよ。イルミのどこか投げ遣りな説明にヒソカは目を眇め、やれやれと身に纏っている慣れないスーツを見下ろす。
「せっかくお洒落してきたのに」
「正直、今のヒソカ胡散臭い詐欺師みたいだよ」
イルミの辛辣な物言いに、ヒソカは肩を竦めた。

頚部、それから後頭部に針を刺され絶命した男に歩み寄る。男のそばに落ちていた携帯からは通話相手の声が漏れて聞こえ、バーのマスターに化していたイルミがそれを足で踏むとパキパキとプラスチックの割れる音がした。
「さてと」
客の掃けた店内で一言そう呟き、カウンターの奥にあるバックヤードのドアを開ける。そこには本物のマスターの上に腰を下ろし、先程とは打って変わって不機嫌そうに頬を膨らませているヒソカがいた。
イルミはそんなヒソカを無表情で見下ろし、首を傾げる。
「なんだっけ、彼女はガードが堅い?」
「はずだったんだけどねえ」
「とんだアバズレだね。どうする? 殺すならオレがやっていい?」
実物の女は写真で見た通り、大して見目麗しいわけでもスタイルがいいわけでもない、ただの女だった。でも平凡というわけではない。あれは、自分たちと同じ類の生き物だ。
興味がないわけじゃなかった。でもそれはあのヒソカが勝手に“恋人”に認定した女にではなく、もし彼女を殺したらヒソカがどんな顔をするのか、そっちの方に興味が湧いた。口説くよりも、ヒソカの目の前で殺してみたい。そうイルミは思ったのだ。
「残念だけど、を殺すのはボクの役目だと決まっているんだよ」
死体から立ち上がったヒソカが煩わしそうにネクタイをぐい、と緩める。イルミはしばらく悩んで、針を持っていた片手を下ろした。
「あんなにオレに惚気けておいて、結局殺すんだ」
ヒソカの性格を思えば当然と言えば当然であるが、少しばかり興醒めした気分でイルミがそう言うと、ヒソカはカウンターを出てを口説いた男――自分たちの拙い作戦が失敗に終わった要因である男の背に座った。
「殺さないよ。今は、ね」
「へえ……意外と寛容なんだね、裏切られたのに」
正確に言えばはヒソカの恋人ではないのだから、『裏切られた』というのは少し違うかもしれないが。そう思いながらもわざと裏切られたと強調して言うイルミに、ヒソカは妖しげな笑みを浮かべる。
「ボクはにたくさんの愛を与えたんだ。でも愛は無償じゃない。与えたものはきちんと返してもらわないと不公平だろう」
「よく分かんないけど、ヒソカがそれでいいならいいんじゃない」
「愛は与えて与えられて、そして自らの手で潰してようやく完成するんだ」
イルミは顔を元に戻し、コキコキと首を鳴らした。例えどんな形であろうとも、歪んでいる男の愛など歪なものに決まっている。理解しようだなんて到底思わない。
ヒソカの指示通り、薬は飲ませた。自分が彼女を殺すという選択肢が消えた以上、あとのことはもうヒソカに任せてしまいたいところだ。
「じゃあが待っているから、ボクは行くよ」
ヒソカはそう言ってイルミにひらりと手を振ると店を後にした。彼女が待っているのはヒソカではなく何も分からないまま死んでしまった男なわけだが、イルミにとって二人がこの先どうなるかだなんてもはや何の興味もなかった。

もはや何の興味もなかったのに、朝を迎えイルミの携帯にヒソカから一枚の写真が添付されたメールが届いた。件名も本文も何もなく、イルミは写真を開く。そこにはどこかの店で食事をとるヒソカとの姿があった。
画角からしてヒソカの自撮りだろう。ヒソカの奥で、がフォークを片手にカメラに向かって呆れたように微笑んでいる。それは盗撮ではない、立派な仲睦まじい“恋人同士”のツーショットに見えた。
これから彼女はヒソカから与えられた分と同じだけの愛を返していくのだろうか。有象無象な愛とやらを。
ヒソカが愛を返してもらったと判断したらいずれ彼女は殺されるのだろうが、やはりそれはイルミにとってどうでもいいことなのである。
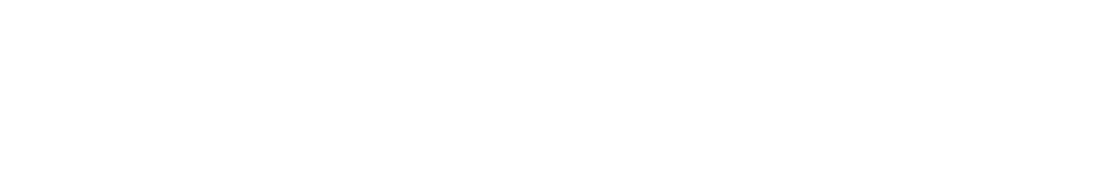

(2024.01.05)